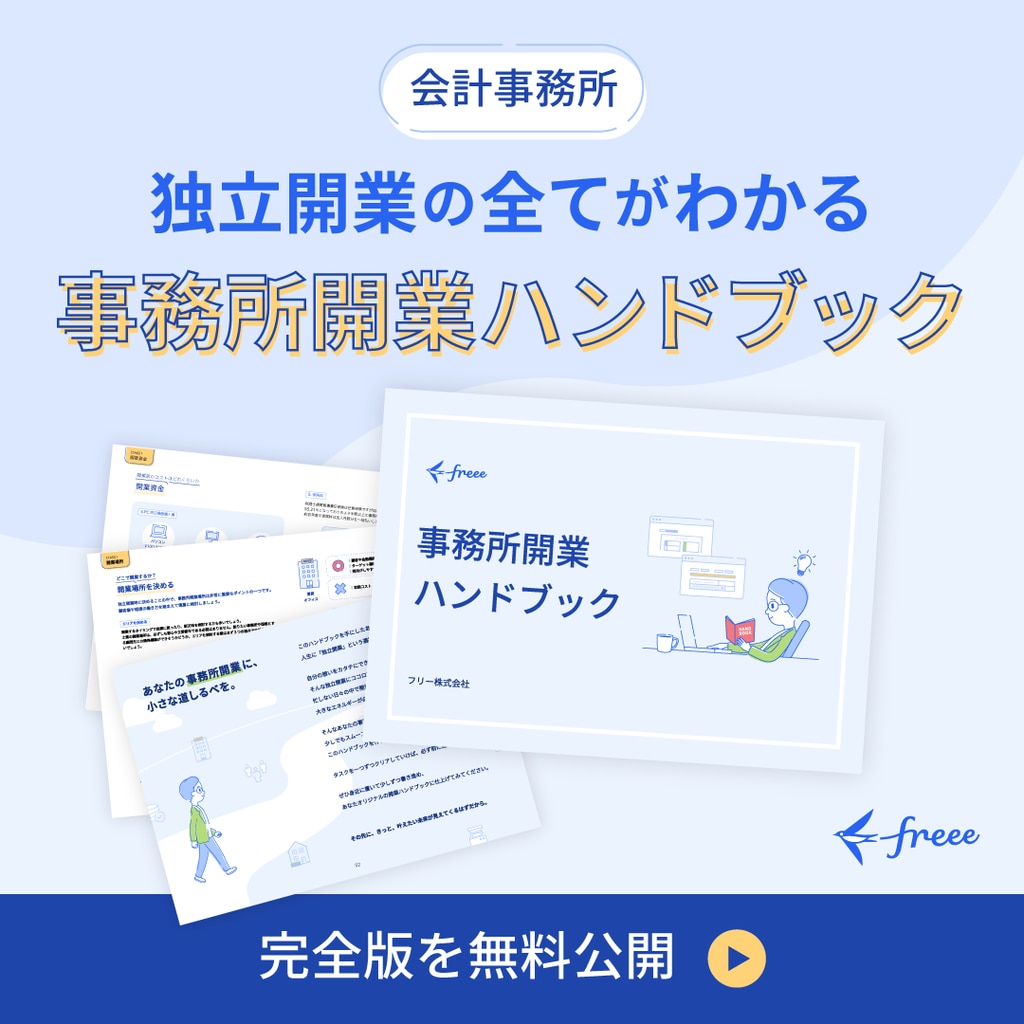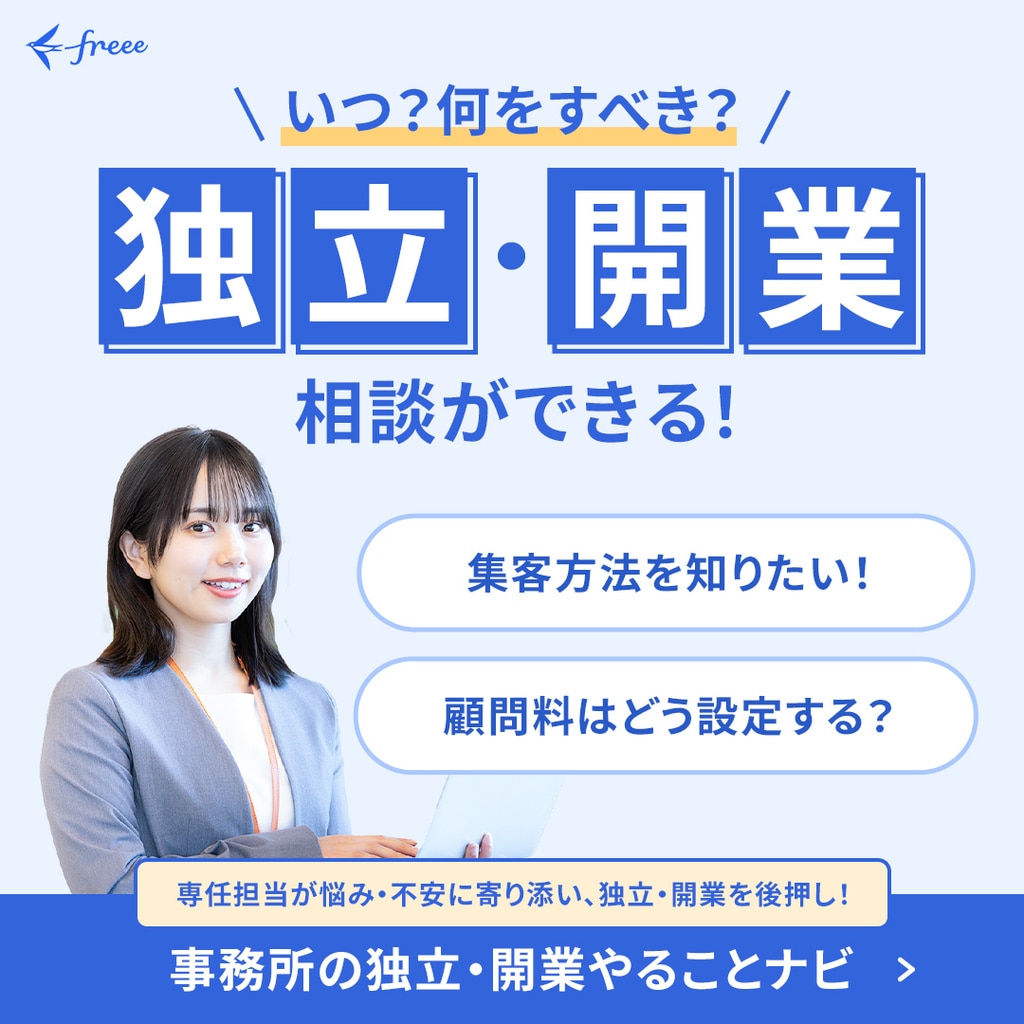税理士の平均年齢と高齢化の実態|若手に広がる活躍の場
PR:独立開業をお考えの方におすすめの資料ダウンロード
・「事務所開業ハンドブック」
・「Web集客で失敗しないためのSEO‧MEOスタートガイド」
税理士業界の平均年齢は60歳前後といわれ、他の士業と比べても高い水準にあります。数字だけを見ると、「若手の活躍の場は少ないのでは」「ベテランばかりが選ばれるのでは」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、高齢化は顧客ニーズではなく、業界特有の構造的な要因によるものです。むしろ、ベテラン税理士の引退や顧客ニーズの多様化、クラウド会計やAIの普及といった環境の変化は、若手税理士にとって活躍のチャンスとなっています。
本記事では、税理士業界の平均年齢や高齢化の理由を確認しつつ、若手がどのように強みを発揮し、開業税理士としてキャリア形成のチャンスを広げられるのかを解説します。
目次[非表示]
税理士の平均年齢と年齢分布
税理士の平均年齢は60歳前後とされています。これは他の士業と比べても高く、業界の大きな特徴のひとつです。
日本税理士会連合会が作成した学生向けパンフレット「税理士になろう」で紹介されている「データで見る税理士」では、過半数が60歳代以上でした。20代は0.6%、30代は10.3%にとどまり、若手の割合は極めて少ない状況です。
【学生向けパンフレット「税理士になろう」のp.9「データで見る税理士」より(※1)】
年代 | 構成割合 |
20歳代 | 0.6% |
30歳代 | 10.3% |
40歳代 | 17.1% |
50歳代 | 17.8% |
60歳代 | 30.1% |
70歳代 | 13.3% |
80歳代 | 10.4% |
(※1)日本税理士連合会|学生向けパンフレット「税理士になろう」(令和5年9月作成)から作成(PDF6/9)9ページ目
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/prospects/zeirishikai_pamph_R509.pdf
税理士の平均年齢が高い理由
先程のデータからも分かるように、税理士の年齢分布は60歳代以上に偏っています。
このようなデータを見て、「経験豊富なベテランしか選ばれないのでは」「若手には活躍の余地がないのでは」と不安に感じる人もいるでしょう。
しかし、税理士業界の高齢化は顧客のニーズによるものではなく、試験制度や後継者問題など、業界特有の構造的な要因から生じるものです。
ここからは、税理士の平均年齢が高い理由を一つずつ見ていきましょう。
試験が免除される国税OBの存在
税務署や国税局に長年勤務した国税職員は、一定の条件を満たすと税理士試験の一部、あるいはすべてが免除されます。
- 10年または15年以上勤務 → 税法科目を免除
- 23年または28年以上勤務+指定研修修了 → 会計科目を免除
この制度により、長年の勤務を終えた国税OBが50代や60代で税理士登録するケースが生じます。こうした仕組みが、平均年齢を押し上げる一因となっています。
長期化しやすい試験制度
税理士試験は科目合格制であり、原則として5科目の合格が必要です。一度にすべてを合格する必要はないため、多くの受験者は1科目ずつ、働きながら数年かけて合格を積み重ねていきます。
その結果、合格まで7〜10年を要することも珍しくなく、必然的に合格年齢は高くなります。
実際に国税庁の合格者のデータでも、5科目合格者では「41歳以上」(最高齢の区分)が約4割を占めています。
【近年の5科目到達者数のうち41歳以上の割合】
5科目到達者数 (A) | (A)のうち、41歳以上 (B) | 割合 (B)/(A) | |
2021年度 | 585 | 256 | 44% |
2022年度 | 620 | 274 | 44% |
2023年度 | 600 | 269 | 45% |
2024年度 | 578 | 229 | 40% |
国税庁|税理士試験(各年度の税理士試験結果より作成)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
定年制度がない
税理士には定年制度がなく、健康であれば70代や80代でも現役で働き続けることができます。
このことから、年齢を重ねても引退しない人が多く、結果として平均年齢の上昇につながっています。
引き継ぎ先がない
高齢になっても、顧問先を引き継いでくれる新しい事務所が決まらないうちに引退することは、心情として難しいものです。
特に、税理士事務所を承継できるのは有資格者に限られるため、後継者を見つけること自体が難航する場合も少なくありません。
適任者が見つかるまで働き続けるしかなく、引退のタイミングを逃しているケースもあると考えられます。
高齢化する業界だからこそ若手に求められる役割
ここまで見てきたとおり、税理士の高齢化は業界特有の構造的な問題によるものです。
むしろ希少な若手だからこそ、さまざまな役割を果たすことができます。
そもそも、顧客は必ずしも税務経験の豊富さだけを税理士に求めているわけではありません。
たとえば、若い経営者が率いるスタートアップにとって、「知識や経験は豊富でも新しいビジネスに疎い税理士」や「税務には強いが創業期の支援には関心がない税理士」では物足りないことがあります。
仮に開業したばかりの若い税理士であっても、スピード感のあるレスポンスやトレンドへの感度を持ち、自身のビジネスを長期的に支援してくれる存在であれば、むしろ若手の方が歓迎されることも少なくありません。
他にも、多くの中小企業にとって、DXによる業務効率化は課題の一つです。クラウド会計の導入支援や各種業務ツールとの連携など、デジタルツールに慣れた世代ならではの仕事術も、中小企業の経営者が期待するポイントになっています。
さらに、高齢のベテラン税理士には、事務所を承継してくれる若手税理士を探しているケースもあります。うまくマッチングできれば、既存の顧客や優秀なスタッフを引き継ぐことができ、事業拡大のチャンスになるかもしれません。
独立を目指す若手税理士が活かせる強み
若手としての強みを活かすには、「若手だからこそ持ち得る強み」をどう発揮するかが鍵となります。
ここでは、独立を目指す若手税理士が、高齢の税理士と差別化を図りやすい、具体的なポイントを解説します。
SNSや動画による情報発信による集客
XやYouTubeなどを活用した情報発信は、税理士にとっても効果的な集客手段です。投稿内容や話し方、他者とのやり取りを通じて人柄が伝わりやすく、見込み顧客に親しみを持ってもらえます。
紹介やポータルサイトに頼りがちなベテラン世代に比べ、デジタル発信を積極的に使いこなせる若手は、自ら顧客との接点をつくりやすいという強みがあります。
SNSの活用のより詳しい記事は「税理士が集客手段としてSNSを利用する際に意識すべきポイントとは 」に掲載しています。ぜひ参考にしてください。
クラウド会計・AIツールによる効率化
クラウド会計による帳簿チェックや金融機関データの自動取り込み、AIによる自動仕訳などにより、会計事務所の業務は大きく効率化されています。
これらを活用し、そこで生まれた時間を経営コンサルティングなど付加価値の高い支援に充てる事務所とそうでない事務所との間で、成長速度の差が広がりつつある状況です。
テクノロジーを積極的に活用し、顧客のニーズに合わせた価値の高いサービスの提供にどんどん挑戦していけるのも、若手税理士の強みといえるでしょう。
柔軟な働き方や新しい価値の提供
リモート顧問やオンライン相談など時代に合わせた働き方に、抵抗感なく対応できることも若手ならではの強みです。
特に経営者には、年齢を問わず、新しいサービスや若い人の価値観の変化に敏感な人がたくさんいます。
若手税理士が持つフレッシュな視点や感覚は、むしろ魅力として受け止められることもあり、立派な強みとなり得ます。
同世代経営者との信頼関係構築
創業したばかりの若い経営者にとって、同世代の税理士は「相談しやすいパートナー」です。
同世代ならではの共通の価値観を持ち合わせていたり、ライフステージの変化など共通の話題も多いため、自然と距離を縮めやすいといえます。
こうした若い経営者の創業支援のチャンスが多いことも、若手税理士の強みといえます。
高齢化は若手にとって大きなチャンス
税理士業界は、平均年齢が60歳前後と高く、若手が極めて少ないという特殊な構造を抱えています。
一見「若手が独立するのは不利」と思われがちですが、実際には逆です。平均年齢が高いからこそ、若手は差別化しやすく、活躍の余地が広がっています。
近年は、クラウド会計やAIツールの普及、事務所承継やM&Aの増加、リモート顧問・オンライン相談といった新しい働き方の広がりなど、業界を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした変化に柔軟に対応できる若手税理士であれば、すぐに顧客に必要とされる存在になれるでしょう。
今後長く活躍するためには、将来を見据えたキャリア戦略が欠かせません。時代が変わっても必要とされる税理士を目指し、独立への一歩を踏み出しましょう。
なお、freeeでは税理士の独立開業を目指す方に向けて、開業準備に必要な情報をまとめた「事務所開業ハンドブック」を無料で提供しています。独立を検討している若手税理士の方は、ぜひ参考にしてみてください。