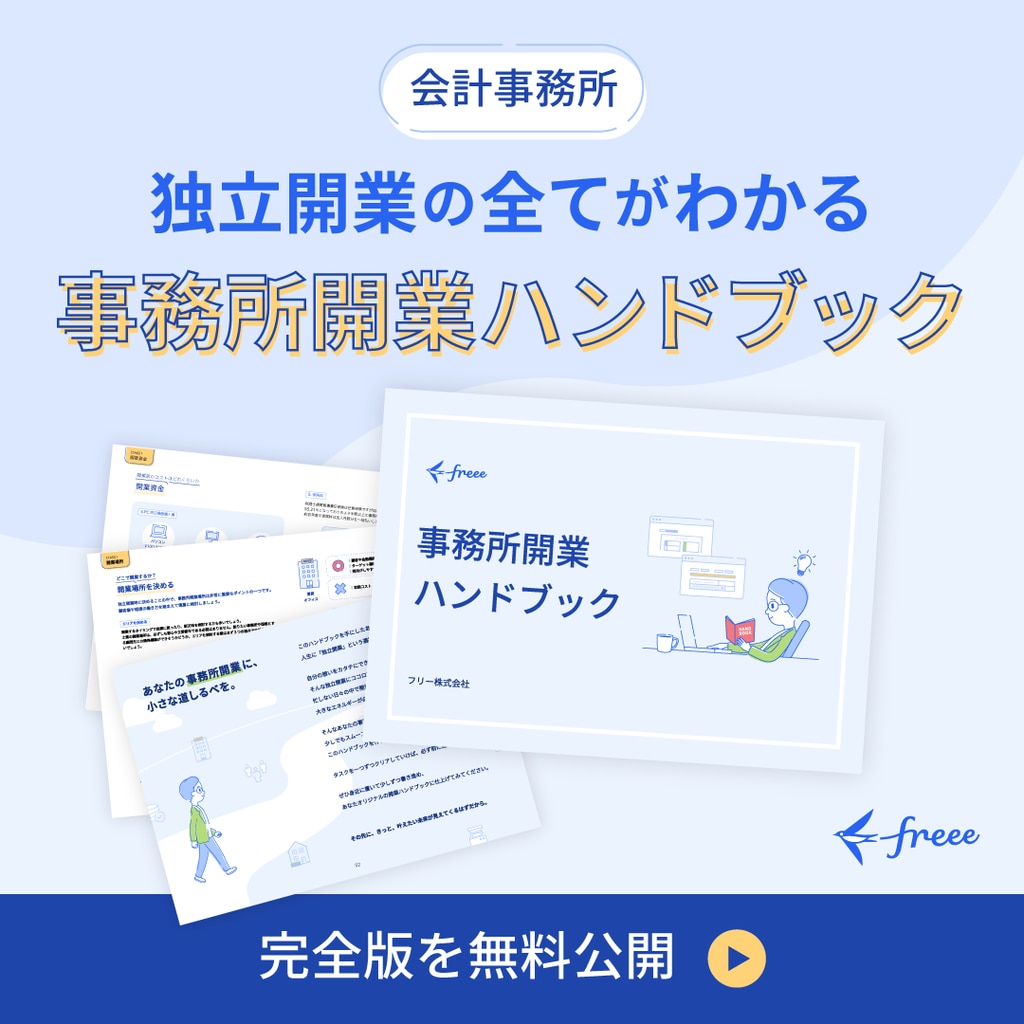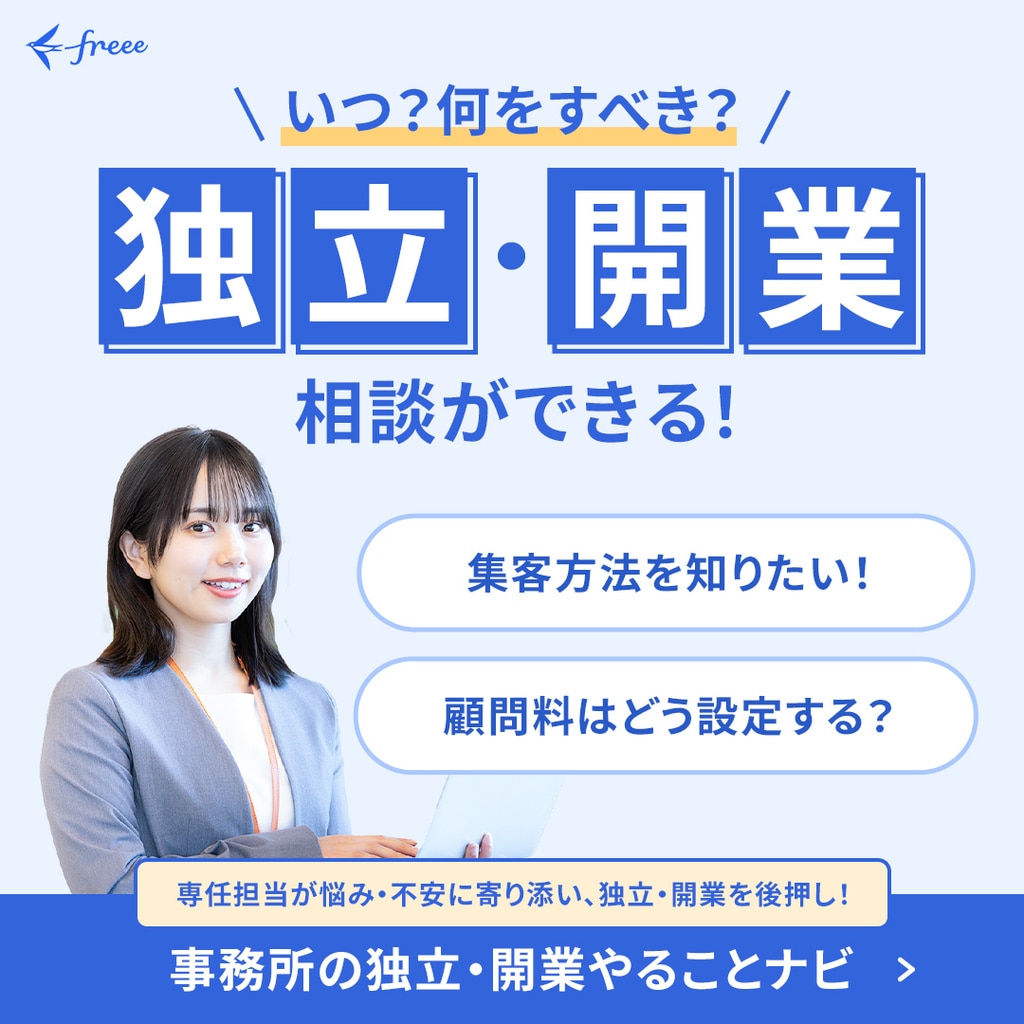税理士の独立開業までの流れ
PR:独立開業をお考えの方におすすめの資料ダウンロード
・「事務所開業ハンドブック」
・「Web集客で失敗しないためのSEO‧MEOスタートガイド」
税理士の中には独立して成功を収める人も少なくありません。とはいえ、独立には準備が必要です。何に費用がかかるかも気になります。今回は、税理士の独立までの流れと最低限かかる費用、そして成功するためのポイントを紹介します。
目次[非表示]
- 1.税理士の独立までの流れ
- 1.1.税理士登録・変更と開業の手続き
- 1.1.1.登録と同時に開業する場合
- 1.1.2.所属税理士・社員税理士が開業する場合
- 1.2.独立の資金を作る
- 1.3.独立に向けた準備をする
- 2.独立に最低限必要なものと費用
- 2.1.税理士登録・変更の費用
- 2.2.ITツール
- 2.3.パソコン周辺機器・通信機器
- 2.4.広告・宣伝
- 2.5.事務所家賃など
- 3.開業資金の調達方法
- 4.税理士が独立して成功するためのポイント
- 4.1.コスト意識を持つ
- 4.2.顧客の獲得につながる活動をする
- 4.3.先人から学ぶ
- 5.開業準備の情報をまとめたハンドブックを配布しています
税理士の独立までの流れ
最初に、税理士の独立までの流れを確認しましょう。
税理士登録・変更と開業の手続き
税理士として最初から独立するなら税理士登録だけですみます。しかし、他の税理士法人の所属税理士か社員税理士になっているのなら、区分の変更の手続きも必要です。東京税理士会の例となりますが、開業するときは、次の書類を税理士会に提出します。
登録と同時に開業する場合
- 変更登録申請書
所属税理士・社員税理士が開業する場合
- 変更登録申請書
- 変更登録申請に関する届出書
この他、事務所を設置する地域を管轄する税務署に開業届等の提出が必要です。
一般的に税理士登録の申請から登録完了までに2〜3ヶ月かかるため、開業を予定している方は、この期間を考慮したスケジュールを立てる必要があります。
税理士登録は複雑で時間もかかる手続きです。freeeでは、税理士登録の手続きの進捗管理や、必要書類の作成、記載項目に対する細かな留意点までフォローする無料サービス「freee税理士登録申請ナビ」を提供しています。すぐに税理士登録をする方はもちろん、税理士登録の手続きの流れを知りたい方にも参考になる点が多いはずです。
独立の資金を作る
事業には資金が必要ですが、税理士も例外ではありません。独立当初は顧客がゼロでも、登録費用や設備投資、営業でお金がかかります。「自宅開業か事務所を借りるか」「設備投資をどこまでするか」などでコストが変わりますが、資金はあるに越したことはありません。「勤務時代に少しずつ貯める」「創業融資を活用する」などで対処していきます。
関連記事:「開業税理士が融資を受ける際の融資元の選択肢とは」
独立に向けた準備をする
独立に向けてできる準備はしておきましょう。例えば事務所です。税理士は独立して業務を行うにあたり、事務所を設けなくてはなりません(税理士法第40条第1項)。
こういった物件は独立前から探しておくと、独立後の時間を節約することができます。
この他「ウェブサイト作りに着手する」「チラシや名刺を作成する」などもできます。独立に必要な作業を箇条書きにし、事前にできそうなことは少しずつやっておきましょう。
関連記事:「開業税理士が新規顧客を獲得するために必要な営業ツール」
独立に最低限必要なものと費用
独立すると、いろいろコストがかかります。どれくらいかかるのかをそれぞれ確認しましょう。
税理士登録・変更の費用
独立するには登録や区分変更が必要です。開業税理士として登録すると、次の費用がかかります。
- 登録免許税…6万円
- 登録手数料…5万円
- 税理士会入会金…4万円(※)
- 会館建設負担金…2万円(※)
- 登録研修のテキスト代…5000円(※)
- 年会費…81,000円(※)
- 支部会費…3万6000円~(支部によって異なる)
(※)東京税理士会の場合
この他、写真撮影代や住民票の写しなどの行政手数料がかかります。税理士登録にかかる費用はこちらで詳しく解説しています。
関連記事:「税理士登録にかかる費用と税理士会の入会金・年会費」
ITツール
税理士の業務には、無償独占業務である「税務代理・税務書類の作成・税務相談」の他、「財務書類の作成・会計帳簿の記帳代行」などがあります。この内、税理士の業務の中心となるのは、申告書などの税務書類の作成や決算書などの財務書類の作成、記帳代行です。
こういった業務は現在、税務申告ソフトや会計ソフトが欠かせなくなっています。また、顧客とのやり取りにチャットツール、業務管理に専用の管理ソフトを使う会計事務所も少なくありません。
ツールの種類によりけりですが、少なくても10~20万円はかかると考えておいた方がいいでしょう。
パソコン周辺機器・通信機器
「今はITツールなしに税理士業務を行えない」とお伝えしました。ITツールを使うなら、当然パソコンやその周辺機器、スマートフォンなどの通信機器も必要です。
最近は、電子帳簿保存法の改正などの影響で、ペーパーレスを意識する税理士が増えています。また、会計ソフトのベンダーも、請求書や領収書をスキャナで読み込むと自動仕訳ができるサービスなどを展開しています。こういったことから税理士業務においてデバイスはますます重要なものとなると見られます。
どこまで用意するか次第ですが、最低20万円は見ておいた方がいいでしょう。
広告・宣伝
独立後、税理士としての認知を高めないと仕事は来ません。最近は無料のSNSで認知度を高め、受注につなげる方法もあります。ただ、提供するサービス全体を知ってもらうなら、看板としてのWebサイトが欠かせません。この他、名刺も必要です。
こういった広告や宣伝にかかる費用は工夫次第で抑えられますが、サーバ代などで2~3万円はかかると考えた方がいいでしょう。
また、税理士の広告には様々なルールが存在します。情報発信の際にはこれらを遵守する必要があります。Webサイトなどでの広告・宣伝を検討する際には改めて確認しておきましょう。
関連記事:「税理士の広告規制とは? 遵守すべき法規則・運用指針を解説」
事務所家賃など
コスト0円で独立するなら自宅事務所がベストですが、業務専用のスペースは必要です。地域によってまちまちですが、月5~10万円は見ておいた方がいいでしょう。コストを抑えた自宅開業でもかまいませんが、業務に集中できる環境や顧客への印象、セキュリティといった観点からは外に事務所を借りた方がベストです。賃貸オフィスのコストを抑えるためには、レンタルオフィス・シェアオフィスといった選択肢もあります。開業場所に適した立地やエリアなど、ビジネススタイルに合わせた選択ができるメリットもあります。
下記の記事では、自宅開業・賃貸オフィスなど、開業条件ごとに資金の目安を解説しています。ご自身の事業計画に合わせて参照してください。
初期費用:「税理士が開業するときに必要な資金は?」
運転資金:「税理士が開業時に準備しておく運転資金 期間・項目・費用試算 」
スタッフ採用:「税理士事務所のスタッフ採用|適切なタイミングと費用、直面する課題」
開業資金の調達方法
税理士として独立すると、何かとお金がかかります。しかし、独立当初は仕事がありません。つまり収入がないのです。けれど現金がなければ事業はストップしてしまいます。こういったことから、あらかじめまとまった事業用資金を準備しておかなくてはなりません。このお金の用意のしかたには、次の2つがあります。
自分で貯める
独立後、もっとも頼りになるのは自分の貯金です。事業の運営資金としてはもちろんのこと、精神的な安定を得るためにも必要です。自宅開業などで初期投資を抑えるとしても、生活などを考えたら少なくても400~500万円はあった方がいいでしょう。
返済不要というのが貯金の利点ですが、反面、一度に多額の資金を作れないという欠点があります。独立前に時間をかけてコツコツと積み上げておきたいものです。
創業融資を利用する
独立後、早めに顧客を獲得し、事業拡大していきたいのなら融資を受けるといいでしょう。税理士でも独立したときは創業融資を受けられます。日本政策金融公庫がよく知られていますが、この他、東京都などの自治体でも創業支援の一環として金融機関などと連携した制度融資を行っています。
融資を受けると現金不足で事業が頓挫するリスクが低減します。が、期日には返済しなくてはならない点に注意しましょう。また、借りたお金はあくまで事業用であることを意識しておきたいものです。
関連記事:「開業税理士が融資を受ける際の融資元の選択肢とは」
税理士が独立して成功するためのポイント
税理士が独立して成功するには、次の2つがポイントとなります。
コスト意識を持つ
独立したら何かと費用がかかります。投資は必要なことですが、不必要なものにお金を払ってしまうことがあります。見栄や不安、焦りが人間にはあるからです。しかし、現金がなければ事業は続けられません。コスト意識がなければ、あっという間に現金が枯渇してしまうのです。
事業の費用については、その都度「これは本当に必要か」「節約する方法はないか」と考えるようにしましょう。
顧客の獲得につながる活動をする
独立したら「開業税理士であることを知ってもらう」ことが大事です。そのため、積極的に他の人と交流するようにしましょう。
税理士会の支部会務は、人脈作りに有効です。総会などに積極的に参加したり、会務を引き受けたりするといいでしょう。その内「こういう仕事、できる?」と声をかけられるかもしれません。
またWEB記事執筆やセミナー講師も認知を高めるチャンスです。自分の存在を知ってもらい、依頼につなげる努力をしましょう。
先人から学ぶ
すでに成功した先輩税理士から学ぶのも一つの方法です。成功の仕方は人それぞれなので、すべてが当てはまるとは限りません。しかし何かしらのヒントはあります。先人の経験談を聞き、気になったことから順に試していくといいかもしれません。
税理士会や、有志の税理士が主催するコミュニティなどで先輩税理士との人脈を得ることができます。会計ベンダーなど関連企業が主催するコミュニティも活発に活動しています。「同じ製品・サービスのユーザー同士」という前提を共有している税理士同士で、実務的なアドバイスも受けることができます。たとえば、freeeでは
実務の疑問を先輩アドバイザーに相談できるコミュニティ「アドバイザー×アドバイザー相談会」を主催しています。
開業準備の情報をまとめたハンドブックを配布しています
freeeでは、税理士として開業を目指す方のために独立開業時に準備すべきことのすべてが分かる「事務所開業ハンドブック」を提供しています。
事業イメージやミッション・ビジョンの策定から具体的な開業への段取りはもちろん、顧問報酬表サンプルほか参考になる資料、開業のロールモデルとなる先輩税理士の実名での事務所事例の紹介など、開業時に必要な情報を網羅しています。
下記のバナーから入力フォームへ移動し、必要事項をご入力、ご送信ください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にすぐに資料ダウンロード用のURLが送付されます。
 開業時の不安を少しでも無くし、皆様の理想事務所を実現するために、是非手に取っていただきたいコンテンツですので、本記事と合わせてぜひご参照ください。
開業時の不安を少しでも無くし、皆様の理想事務所を実現するために、是非手に取っていただきたいコンテンツですので、本記事と合わせてぜひご参照ください。