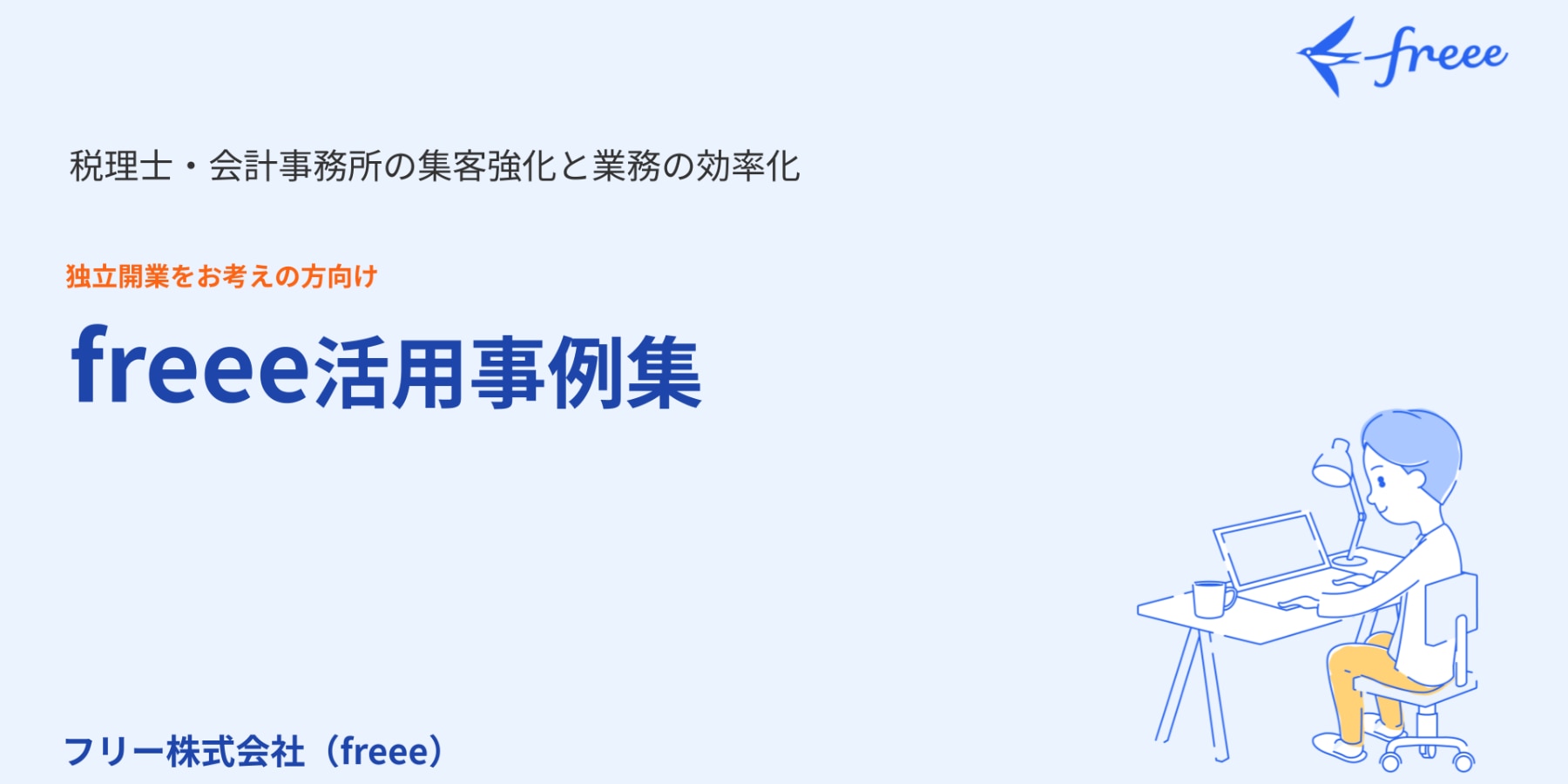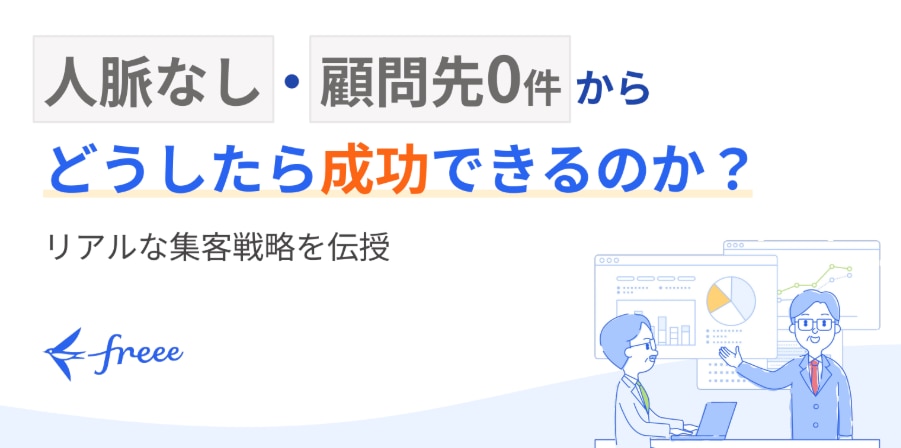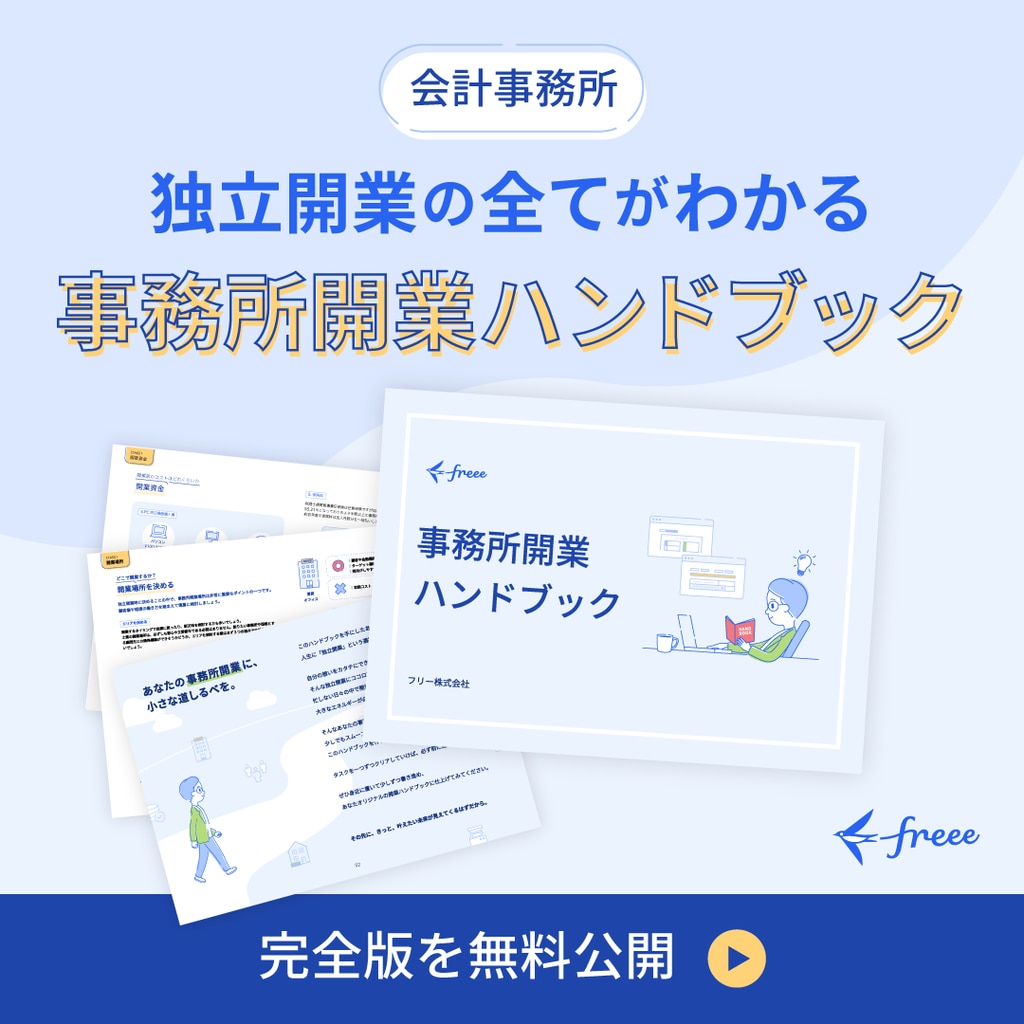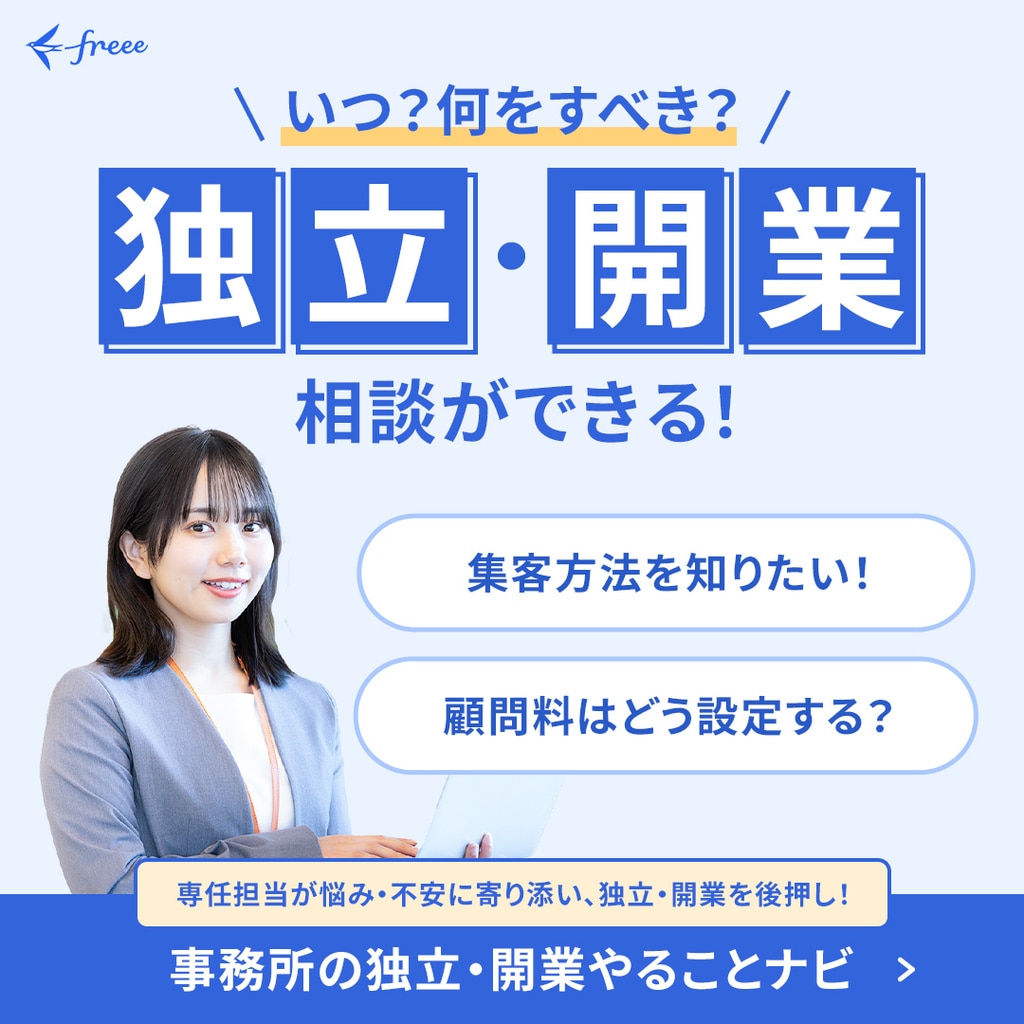税理士法人の特徴とメリット|開業後に法人化を検討するタイミング
独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード
近年、税理士登録者の数は8万人を超え、このうち2024年度末における「社員税理士」の数は13,734人、税理士法人の数は5,146件、従たる事務所(いわゆる支店)の数は2,935件となりました(※1)。
税理士法人は、組織規模の拡大や事業承継のしやすさといったメリットを持ちます。そのため、個人事務所を経営する税理士の中には「将来は法人化すべきか」と悩む方も少なくありません。
本記事では、税理士法人の定義や仕組み、個人事務所との違いを整理したうえで、法人化のメリット・デメリットを具体的に解説します。さらに、どのようなタイミングで法人化を検討すべきかの判断基準や、キャリア形成における位置づけについても紹介します。
「個人事務所と税理士法人の違いを知りたい」「法人化を検討すべきか迷っている」という方は、ぜひ参考にしてください。
(※1)国税庁|日本税理士会連合会
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm
目次[非表示]
税理士法人の概要
税理士法人とは、税理士業務を組織的に行うための法人です。その経営者を自然人である税理士に限定する特別法人となります。2001年(平成13年)の税理士法改正により、「2名以上の税理士」による共同経営を条件に設立できるようになりました(※2)。
最大の利点は、業務を組織的かつ継続的に提供できることです。個人事務所では、所長が引退すると廃業につながりますが、税理士法人なら他の税理士が経営を引き継ぎ、事務所を継続できます。また、個人税理士に課されている「二箇所事務所の禁止」の制約を受けず、社員税理士が常駐する従たる事務所(支店)を展開することも可能です。これにより、個人事務所では難しい分業や広域展開が実現できます。
税理士法人の詳しいメリットは、「税理士法人と個人税理士事務所の違い」で説明します。
(※2)税理士法第四十八条の二(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2-At_48_2
税理士法第四十八条の十八第一項(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2-At_48_18
税理士法基本通達48の8-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm
税理士法人に所属する税理士
税理士法人に所属する税理士は、大きく「社員税理士」と「所属税理士」に分かれます。
社員税理士は法人経営に関与する立場であり、所属税理士は法人に雇用されて業務を担います。両者とも税理士業務を行えますが、権限や責任の範囲には違いがあります。
それぞれの詳細や区分の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:税理士の登録区分3種類をわかりやすく解説|特徴と働き方の違い
税理士法人と個人税理士事務所の違い
税理士法人と個人事務所は、制度や仕組みに大きな違いがあります。ここでは「規模」「信用力」「人材活用」「事業承継」の観点から比較します。
規模
個人の税理士は、2つ以上の事務所を設置できず、拠点は原則1か所に限られます。顧客やスタッフを増やそうとしても、場所やスペースの制約を受けます。
一方、税理士法人は社員税理士の常駐を条件に複数拠点を設置でき、支店展開や他事務所との統合が可能です。これにより、広域展開や売上規模の拡大にも積極的に取り組めます(※6)。
(※6)税理士法第四十条第三項、第四十八条の十二(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_4-At_40
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2-At_48_12
信用力
個人事務所は、所長が業務を続けられなくなると廃業につながります。そのため、所長の高齢化とともに顧問先や従業員が不安を抱くこともあります。
これに対して税理士法人は、新たに社員税理士を迎えることで業務継続が可能です。組織の安定性から、顧問先や従業員の安心感だけでなく、金融機関からの信用力も高まります。
人材活用
税理士事務所の基盤は「人」です。税理士法人は規模や信用力の点で、個人事務所よりも優秀な人材を確保しやすいといえます。
また、部門制を導入し責任者を配置することで、業務効率やスタッフの専門性を高められます。こうした体制が機能すれば、人材育成が進み、組織全体の生産性向上につながります。
事業承継
個人事務所の承継では、一度廃業してから後継者に引き継ぐため、顧問先が他の税理士に流れたり従業員が退職したりするリスクがあります。
一方、税理士法人では代表社員を交代させるだけで顧問契約や労働契約を承継でき、円滑で安定的な事業承継が可能です。
独立後に法人化を検討するメリット
法人化により、信用力・採用力・多拠点展開・承継の平滑化・税務最適化が実現しやすくなります。主要メリットを以下に整理します。
信用力の向上
組織としての持続性が評価されやすく、金融機関との与信や大手・中堅企業との取引で有利に働きます。とくに創業初期の営業や資金調達では、「個人ではなく法人」という看板が初期信頼の形成を加速させます。
組織規模の拡大
多拠点展開や部門制の導入により、役割分担とレビュー体制を組み込みやすくなります。これにより、属人化の解消、業務効率の向上に加え、品質の平準化まで実現しやすくなります。
人材採用・育成のしやすさ
社会保険・福利厚生の整備、等級・評価制度の導入が進めやすく、採用競争力と定着率が向上。体系的な研修・OJTを回せるため、育成→定着→戦力化の循環を作りやすくなります。
事務所承継の円滑化
代表交代のみで事務所を存続でき、顧問契約・雇用契約を維持しやすい点が強み。結果として、解約・退職リスクの最小化に直結し、顧客・従業員の安心感が高まります。
独自の組織づくりができる
ゼロから理想の組織を構築できる点も法人化の魅力です。信頼できるパートナーと協力して組織体制を設計し、採用や育成の方針を自ら決めることで、自分の経営理念を反映させた事務所運営が可能になります。さらに、大手税理士法人の傘下に入る選択をすれば、ブランド力やノウハウを活用して短期間で事業基盤を安定させることもできます。
節税効果が得られる
役員報酬設計や法人税率の活用により、一定の利益水準からは個人より有利になりやすい構造です。さらに福利厚生費や将来投資の計上余地が広がり、資金繰りの安定化にもつながります。
独立後に法人化を検討する際の注意点
個人事務所を税理士法人にすることで多くのメリットが得られますが、その一方で設立コストや組織運営の難しさなどに注意が必要です。
設立・運営コスト
税理士法人の設立には約30万円の初期費用がかかります。
- 司法書士への登記依頼:約15万円
- 税理士会の手続き(登録区分の変更、社員資格証明書交付、設立届出、本会費・支部会費など):約15万円
さらに、法人化後は税理士法人の会費や社会保険料といった運営コストが継続的に発生します。
組織運営の複雑化
税理士法人は2名以上の社員税理士で運営する必要があります。
- 社員税理士はそれぞれ業務執行権を持つため、経営方針は話し合いで決定することが基本
- 定款変更や社員の入退社など、全員の同意が必要な事項もあり、意思決定に時間がかかる場合がある
- 人数や関係性によっては意見がまとまらず、不和の原因になることもある
社員税理士の確保
税理士法人は、2名以上の社員税理士が常に在籍していなければなりません。1名だけの状態が6か月続くと、法人は解散となります(※7)。
また、社員税理士は無限連帯責任を負うため、新たな社員をすぐに見つけるのは容易ではありません。そのため、「定期的な情報共有の仕組み」や「賠償責任保険の活用によるリスクヘッジ」といった備えをしておくことが重要です。
(※7)税理士法第四十八条の十八第一項(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2-At_48_18
独立後の将来像を見据えて法人化を選択肢に
税理士法人は、税理士にとって必ず選ばなければならない道ではありません。しかし、キャリアや事務所の成長段階に応じて検討すべき有力な選択肢であることは確かです。
法人化によって得られる信用力や人材活用のしやすさなどのメリットは、将来の経営を安定させる大きな力となります。一方で、法人化にはコストや組織運営の複雑さといったデメリットも伴います。
まずは個人事務所として小規模にスタートし、基盤を固めたうえで、次のステップとして法人化を検討することも有効な戦略です。
なお、freeeでは税理士の独立開業を目指す方に向けて、開業準備に必要な情報をまとめた「事務所開業ハンドブック」を無料で提供しています。独立後の将来像を描くうえでの参考資料として、ぜひご活用ください。
独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード