伴走型の自計化、1人で90社を支援。データマネジメントで実現する最適な事務所運営

天野会計事務所
代表 天野 徹 様
事務所規模:1名
所在地:神奈川県横浜市
課題:業務効率化、付加価値向上
事務所規模:1名
所在地:神奈川県横浜市
課題:業務効率化、付加価値向上
■freee導入前に抱えていた課題
- 1人事務所を運営する上で手入力には限界を感じる
- 記帳業務の経験が多くない
- 顧問先の自立支援と最適な事務所運営の両立が必要
■実践したこと/効果
- データを最大限活用することで、顧問先の財務会計のみならず経営面までサポート
- 自動登録(仕訳)ルールのセットアップとコーチング型指導で、顧問先の自計化を実現
- 完全オンライン対応、かつイレギュラーな個別対応は最小限に抑え、最適なコミュニケーションを確立
多くの会計事務所が顧問先ごとの要望の違いに苦心する中、天野会計事務所は自計化、オンライン対応、ペーパーレス運営などの方針を明確に打ち出し、「データ統合ソフト」という発想でfreee会計を活用することで最適な支援を実現しています。
今回は代表の天野徹さんに、顧問先との付き合い方やfreee会計導入背景、外資系企業での経験を活かした新しい事務所運営のあり方について話を伺いました。
今回は代表の天野徹さんに、顧問先との付き合い方やfreee会計導入背景、外資系企業での経験を活かした新しい事務所運営のあり方について話を伺いました。
デジタル化の早い外資系企業の経験と、freee会計の設計思想がマッチした
――現在の事務所の方針と強みを教えていただけますか。
天野 徹さん(以下、天野):事務所の方針として、「自動化に近い自計化」「オンライン対応」「ペーパーレス運営」などを決めています。特に、「自動化に近い自計化」については、他の会計事務所とは異なる特徴かもしれません。
私はfreee会計を「会計ソフト」ではなく、世の中に存在するデジタルデータを集めて活用する「データ統合ソフト」として捉えています。銀行取引やクレジットカードのデータを取り込み、そこから会計データを作り上げていくという考え方が、自計化・業務最適化の大きなポイントになっています。
また、顧問先とのやり取りはオンラインに限定し、電話は受けずにチャットツールのみで対応しています。
そのうえで私自身は1日の業務時間を4時間以内と決め、残りの時間はセミナーへの参加や勉強など、新しい知識の習得に充てています。
それでも税理士1人の体制で90社(個人15を含む)の顧問先を受け付けることができています。
私はfreee会計を「会計ソフト」ではなく、世の中に存在するデジタルデータを集めて活用する「データ統合ソフト」として捉えています。銀行取引やクレジットカードのデータを取り込み、そこから会計データを作り上げていくという考え方が、自計化・業務最適化の大きなポイントになっています。
また、顧問先とのやり取りはオンラインに限定し、電話は受けずにチャットツールのみで対応しています。
そのうえで私自身は1日の業務時間を4時間以内と決め、残りの時間はセミナーへの参加や勉強など、新しい知識の習得に充てています。
それでも税理士1人の体制で90社(個人15を含む)の顧問先を受け付けることができています。

――freee会計を導入された背景は何だったのでしょうか。
天野:実は私は、税理士資格は持っているものの、会計事務所で仕訳入力を行うなどの経験は多くありません。
以前はKPMG(世界4大会計事務所の一角)で10年勤務しましたが、その後アメリカの事業会社2社で合計20年ほど経理畑を歩んできました。
開業当初は、複数のクラウド会計ソフトを使い比較していたのですが、自分で入力作業をしてみて「これを1人事務所で請け負うのは難しい」と感じました。会計事務所として、記帳代行ではなく、自計化の方向に進もうと決めたのです。その後はfreeeに統一し、freeeを使っている顧問先だけを受けるようにしました。
これには、前職での経験が大きく影響しています。事業会社では受注から製造・販売・その後のサポートまで、データが自然に流れるERPの仕組みができていました。
会計業務はそのデータから必要なものを取り込んで決算書を作ること。仕訳入力による帳簿付けはあくまでも補助的な手段のひとつでした。
前職では経費精算も、営業担当者がスマートフォンで撮影した領収書データを送っており、多くの部分がデジタル化されていました。そういった環境に慣れていたため、freeeのシステムは非常に肌に合っていたのだと思います。
以前はKPMG(世界4大会計事務所の一角)で10年勤務しましたが、その後アメリカの事業会社2社で合計20年ほど経理畑を歩んできました。
開業当初は、複数のクラウド会計ソフトを使い比較していたのですが、自分で入力作業をしてみて「これを1人事務所で請け負うのは難しい」と感じました。会計事務所として、記帳代行ではなく、自計化の方向に進もうと決めたのです。その後はfreeeに統一し、freeeを使っている顧問先だけを受けるようにしました。
これには、前職での経験が大きく影響しています。事業会社では受注から製造・販売・その後のサポートまで、データが自然に流れるERPの仕組みができていました。
会計業務はそのデータから必要なものを取り込んで決算書を作ること。仕訳入力による帳簿付けはあくまでも補助的な手段のひとつでした。
前職では経費精算も、営業担当者がスマートフォンで撮影した領収書データを送っており、多くの部分がデジタル化されていました。そういった環境に慣れていたため、freeeのシステムは非常に肌に合っていたのだと思います。

無理なくイレギュラーの少ない自計化を実現するコーチング型支援
――具体的な業務の進め方を教えていただけますか。
天野:基本的には「自計化」という建て付けで進めています。ただし、顧問先に仕訳入力など多く手を動かしてもらう従来型の自計化とは異なり、「自動化に近い自計化」を目指しています。
手間を最小限に抑えるため、freee会計の最初のセットアップは事務所側で行うようにし、顧問先には「とにかくデータを連携して流し込んで下さい」とお伝えします。
ネット銀行とクレジットカードとの連携を行うことで、自動的に仕訳登録ができるように仕組み化することがファーストステップです。
はじめの2〜3ヶ月分のデータが取れたら、顧問先とオンライン面談をつないで、一緒に確認しながら、自動登録(仕訳)ルールの設定などを行います。最初は私が操作するのを見てもらい、顧問先も徐々に自身で処理できるようになっていきます。
たとえ習得がスローペースだったとしても「次は頑張りましょう」と励ましながら3か月ごとに見ていく。それを続けていくと、1年目の決算が終わる頃には大半の顧問先が自動化に近い自計化を達成できるようになります。
自動登録(仕訳)ルールで処理されたものが基本となりますが、私の役割は、貸借対照表を中心に全体を見たうえで気になるところに「ここの自動登録(仕訳)ルールは適切ですか?変える必要がありますか?」と確認して微調整していくこと。
申告書の内訳明細に必要な貸借対照表の科目には取引先の入力をお願いしていますが、損益計算書は顧問先の業種や、「何を知りたいか」によってアドバイスを変えるようにしています。例えば、「売上の取引先は入力しておいた方が、あとから分析がしやすいですよ」とか、「この経費科目が多くなっていますが、ご自身の感覚と合っていますか?取引先ごと、品目ごとに分けてみますか?」といった確認をするなど、必要な情報を「見える化」できるようにしています。
手間を最小限に抑えるため、freee会計の最初のセットアップは事務所側で行うようにし、顧問先には「とにかくデータを連携して流し込んで下さい」とお伝えします。
ネット銀行とクレジットカードとの連携を行うことで、自動的に仕訳登録ができるように仕組み化することがファーストステップです。
はじめの2〜3ヶ月分のデータが取れたら、顧問先とオンライン面談をつないで、一緒に確認しながら、自動登録(仕訳)ルールの設定などを行います。最初は私が操作するのを見てもらい、顧問先も徐々に自身で処理できるようになっていきます。
たとえ習得がスローペースだったとしても「次は頑張りましょう」と励ましながら3か月ごとに見ていく。それを続けていくと、1年目の決算が終わる頃には大半の顧問先が自動化に近い自計化を達成できるようになります。
自動登録(仕訳)ルールで処理されたものが基本となりますが、私の役割は、貸借対照表を中心に全体を見たうえで気になるところに「ここの自動登録(仕訳)ルールは適切ですか?変える必要がありますか?」と確認して微調整していくこと。
申告書の内訳明細に必要な貸借対照表の科目には取引先の入力をお願いしていますが、損益計算書は顧問先の業種や、「何を知りたいか」によってアドバイスを変えるようにしています。例えば、「売上の取引先は入力しておいた方が、あとから分析がしやすいですよ」とか、「この経費科目が多くなっていますが、ご自身の感覚と合っていますか?取引先ごと、品目ごとに分けてみますか?」といった確認をするなど、必要な情報を「見える化」できるようにしています。

――自計化というと、顧問先の負担を心配される方も多いと思いますが、実際はいかがでしょうか?
天野:最適化しているので、そこまで大きな負担にはなっていないと思いますが、freee会計の操作においては、会計知識のない方にも分かりやすく説明することを心がけています。
例えば、「仕訳」「借方」「貸方」といった専門用語は極力使わず、「入金」「出金」という言葉で説明します。「入出金があったときに連携されたデータをこうやって処理すると、下に自動的にこんな記録(仕訳)が残りますよ」とお伝えする。どうしてもまとまった取引を入れないといけないケースが出てきたら、「エクセルにまとめてシステムに流し込み(インポート)ましょう」と話します。
また、顧問先で判断できない経費処理などは無理に間違った処理を行わず、一時的に「雑費」として処理してもらうようにしています。3か月ごとのオンライン面談で、雑費の項目について内容を確認しながら、適切な科目に振り分けていきます。このように実践しながら覚えていただく方が、理解も早いです。最初から完璧を求めず、少しずつ習熟度を上げていくので顧問先から「負担が重い」と言われることはほとんどありません。
「丸投げしたい」という方はお断りすることもあります。イレギュラーを作ると余計な時間がかかってしまい、結果として他の顧問先にも迷惑がかかるので、freee会計を使った自計化に取り組む意欲のある方に絞ってサービスを提供しています。
例えば、「仕訳」「借方」「貸方」といった専門用語は極力使わず、「入金」「出金」という言葉で説明します。「入出金があったときに連携されたデータをこうやって処理すると、下に自動的にこんな記録(仕訳)が残りますよ」とお伝えする。どうしてもまとまった取引を入れないといけないケースが出てきたら、「エクセルにまとめてシステムに流し込み(インポート)ましょう」と話します。
また、顧問先で判断できない経費処理などは無理に間違った処理を行わず、一時的に「雑費」として処理してもらうようにしています。3か月ごとのオンライン面談で、雑費の項目について内容を確認しながら、適切な科目に振り分けていきます。このように実践しながら覚えていただく方が、理解も早いです。最初から完璧を求めず、少しずつ習熟度を上げていくので顧問先から「負担が重い」と言われることはほとんどありません。
「丸投げしたい」という方はお断りすることもあります。イレギュラーを作ると余計な時間がかかってしまい、結果として他の顧問先にも迷惑がかかるので、freee会計を使った自計化に取り組む意欲のある方に絞ってサービスを提供しています。
――顧問先の要望に応えようとしてイレギュラーが増えてしまう事務所も多いと思います。天野さんはなぜ、そのような運営ができているのですか?
天野:いろいろな税理士さんとお話すると、顧問先というよりも、事務所内が今までのやり方を変えられないケースが多いと感じています。顧問先が求めていることを考えていくと、自ずとすべきことが見えてくるのではないでしょうか。
私は、会計事務所はサービス業だと思っているので、お客さまが求めていることに上手く時間を使う必要があると考えています。
この考え方になったのは、事業会社での経験が大きいと思います。前職時代に業務の最適化を突き詰める中で、スタッフの1日8時間の業務時間のうち、実質的な業務に充てられている時間は4時間程度という事実を突きつけられたことがあります。そのため、自分の業務時間も1日4時間にしようと決めましたし、業務のアウトソーシング化の経験も活きています。
「95%の精度で業務を処理することと、残りの5%を完璧にしていくことは、同程度の労力がかかる、また、時間の経過で95%が100%に近づくが、100%にはならないし100%にする必要もない」と前職で言われたことがります。私はこのことを知ったとき、ハッとして、最適化への意識がより強くなりました。
私は、会計事務所はサービス業だと思っているので、お客さまが求めていることに上手く時間を使う必要があると考えています。
この考え方になったのは、事業会社での経験が大きいと思います。前職時代に業務の最適化を突き詰める中で、スタッフの1日8時間の業務時間のうち、実質的な業務に充てられている時間は4時間程度という事実を突きつけられたことがあります。そのため、自分の業務時間も1日4時間にしようと決めましたし、業務のアウトソーシング化の経験も活きています。
「95%の精度で業務を処理することと、残りの5%を完璧にしていくことは、同程度の労力がかかる、また、時間の経過で95%が100%に近づくが、100%にはならないし100%にする必要もない」と前職で言われたことがります。私はこのことを知ったとき、ハッとして、最適化への意識がより強くなりました。

コロナ禍を経て皆さんオンラインコミュニケーションに慣れたこともあり、年配の経営者であってもオンライン面談やチャットツールはご説明すればしっかり使ってもらえています。
丸投げでは出てきた数字だけを見ることになりますが、自計化は、顧問先自身が日頃から自社の数字に触れることになり、自然と経営判断に必要な感覚が身につくと感じています。
freee会計を活用すれば、現状の確認だけでなく、昨年と今年の実績比較、来期の予算作成などを行えます。それを踏まえて、徐々に3~5年の中期計画を自らの手で作成できる顧問先も増えてきています。こういったことができるのは、「データ統合ソフト」であるfreee会計ならではだと思います。
会計データを税務申告のためだけでなく、いかに経営に役立てるかを考えてもらうようにしています。
丸投げでは出てきた数字だけを見ることになりますが、自計化は、顧問先自身が日頃から自社の数字に触れることになり、自然と経営判断に必要な感覚が身につくと感じています。
freee会計を活用すれば、現状の確認だけでなく、昨年と今年の実績比較、来期の予算作成などを行えます。それを踏まえて、徐々に3~5年の中期計画を自らの手で作成できる顧問先も増えてきています。こういったことができるのは、「データ統合ソフト」であるfreee会計ならではだと思います。
会計データを税務申告のためだけでなく、いかに経営に役立てるかを考えてもらうようにしています。
――まさに“コーチング型”の事務所経営をされていますね。
天野:そうですね。顧問先の「やる気」を引き出しながら、顧問先の成長に合わせて、段階的にサポートを広げることを重視しています。
重要なのは、決して押し付けにならないようにすること。例えば、収益予測機能について一緒に画面を見ながら説明する。その後、「使ってみませんか?」と何度か声をかけ、顧問先が「これなら便利だし、できそうだ」と感じたタイミングで自ら手を動かしてもらうよう勧めます。
おかげさまで1時間の月次(又は四半期)ミーティングでは、会計データのチェックは30分程度で終わらせ、残りの時間は、来年や再来年についてどう考えているかといった、未来への対話の時間に充てることができています。
重要なのは、決して押し付けにならないようにすること。例えば、収益予測機能について一緒に画面を見ながら説明する。その後、「使ってみませんか?」と何度か声をかけ、顧問先が「これなら便利だし、できそうだ」と感じたタイミングで自ら手を動かしてもらうよう勧めます。
おかげさまで1時間の月次(又は四半期)ミーティングでは、会計データのチェックは30分程度で終わらせ、残りの時間は、来年や再来年についてどう考えているかといった、未来への対話の時間に充てることができています。
天野会計事務所を選ぶ顧問先からのコメント
SAISON Office 合同会社 経理担当 木曽様 (写真中央)
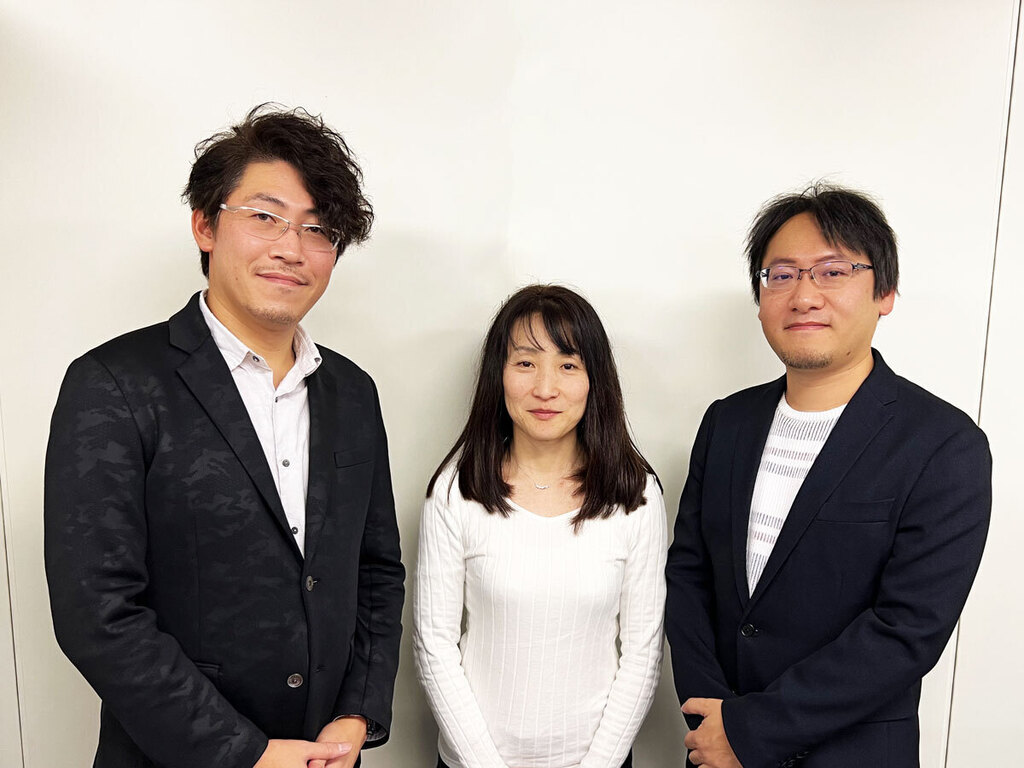
天野先生を選んだ決め手は、決算業務のみの依頼にも柔軟に対応していただけた点でした。多くの事務所では月次監査が必須でしたが、天野先生は快諾してくださいました。
その後、お付き合いが進むにつれ、日々の業務のアドバイスもいただけるようになり、自然と面談の回数も増えていきました。最近はfreeeと連携して予算や実績を管理するツールも使い始めています。
freeeの使い方も幅が広がっています。天野先生に顧問をご依頼する前からfreeeを利用していたので、ある程度操作については熟知しているつもりです。それでも面談の際に天野先生から知らなかった機能や使い方を教わることがあり、これまでよりも経理業務が効率化していると思います。
天野先生は私たちにとって、安心して相談できる存在です。以前の顧問を依頼していた先生は電話やメールの返信に時間がかかっていましたが、天野先生はオンライン面談ですぐに対応していただけます。また3ヶ月に1回は必ず予算と実績の確認をしていただけるので、経営の方向性を常に確認できる安心感があります。新しいツールの活用など、先生に依頼したからこそ、どんどん発展していっていると実感しています。
その後、お付き合いが進むにつれ、日々の業務のアドバイスもいただけるようになり、自然と面談の回数も増えていきました。最近はfreeeと連携して予算や実績を管理するツールも使い始めています。
freeeの使い方も幅が広がっています。天野先生に顧問をご依頼する前からfreeeを利用していたので、ある程度操作については熟知しているつもりです。それでも面談の際に天野先生から知らなかった機能や使い方を教わることがあり、これまでよりも経理業務が効率化していると思います。
天野先生は私たちにとって、安心して相談できる存在です。以前の顧問を依頼していた先生は電話やメールの返信に時間がかかっていましたが、天野先生はオンライン面談ですぐに対応していただけます。また3ヶ月に1回は必ず予算と実績の確認をしていただけるので、経営の方向性を常に確認できる安心感があります。新しいツールの活用など、先生に依頼したからこそ、どんどん発展していっていると実感しています。
DXは既定路線。スモールスタートで広げていく
――会計事務所のDX化について、どのようにお考えでしょうか?
天野:DXは「やるか、やらないか」ではなく「いつやるか」の問題。スマートフォンが携帯電話に取って代わったように、デジタル化の波は確実に来ます。
と言われていますが、私も同感です。
ただ、事務所全体を一気に変えようとするのは難しいものです。私がお勧めするのは、スモールスタートで少しずつ変化を加えていくこと。
例えば、事務所の若手職員1名にfreeeを使ってもらい、新規顧問先を担当させ、所長自身も直接その様子を見ながら自身でも触れて、freeeの便利さを実感する。そこから少しずつ広げていけば、2〜3年で今以上の売上を上げることも可能ですし、他の職員にも良い影響を与えられます。
記帳代行を主体とするなら従来の会計ソフトでも良いかもしれません。
しかし、これからの時代に求められるであろうデータマネジメントの視点を持って価値提供していきたいなら、freeeの活用をお勧めします。職員さん方も、今までの仕事から新しい仕事へとシフトすることで、給与水準を上げながら最適な働き方が実現できるはずです。
と言われていますが、私も同感です。
ただ、事務所全体を一気に変えようとするのは難しいものです。私がお勧めするのは、スモールスタートで少しずつ変化を加えていくこと。
例えば、事務所の若手職員1名にfreeeを使ってもらい、新規顧問先を担当させ、所長自身も直接その様子を見ながら自身でも触れて、freeeの便利さを実感する。そこから少しずつ広げていけば、2〜3年で今以上の売上を上げることも可能ですし、他の職員にも良い影響を与えられます。
記帳代行を主体とするなら従来の会計ソフトでも良いかもしれません。
しかし、これからの時代に求められるであろうデータマネジメントの視点を持って価値提供していきたいなら、freeeの活用をお勧めします。職員さん方も、今までの仕事から新しい仕事へとシフトすることで、給与水準を上げながら最適な働き方が実現できるはずです。

――最後に、これからの展望についてお聞かせください。
天野:日本企業の生産性の低さは、実は会計事務所にも原因があると考えています。
まず私たち自身が先導して業務の最適化を進め、新しい価値を提供できる存在に進化していく必要があるでしょう。コーチング型の支援を通じて、ともに成長していける関係づくりを、これからも大切にしていきたいと考えています。
まず私たち自身が先導して業務の最適化を進め、新しい価値を提供できる存在に進化していく必要があるでしょう。コーチング型の支援を通じて、ともに成長していける関係づくりを、これからも大切にしていきたいと考えています。
天野会計事務所
神奈川県横浜市
freee認定アドバイザーページはこちら
利用サービス
あわせて読みたいその他の事例
課題:業務効率化
導入サービス:freee会計
会計事務所の方
サービス
ご契約者の方はこちら
© 2012 freee K.K.
